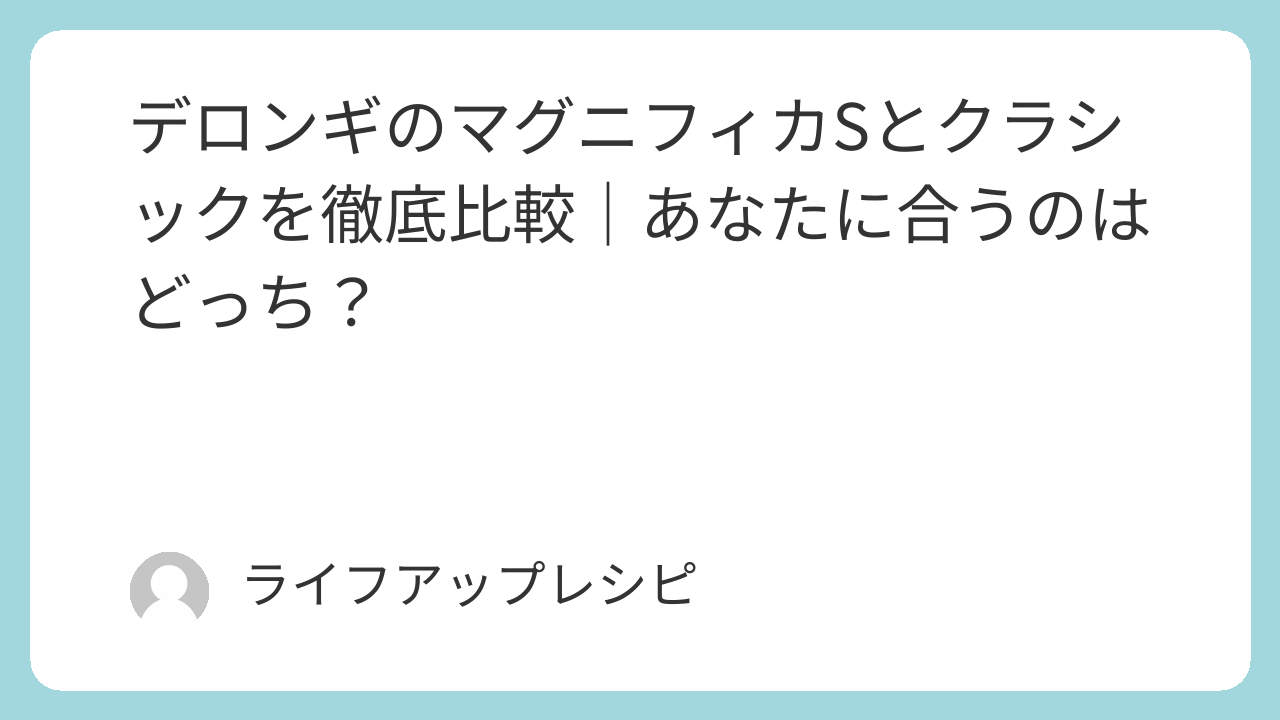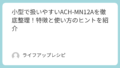デロンギの「マグニフィカS」と「クラシック」。
どちらもよく見かける人気機種なので、違いが分からないまま候補に入ってしまう方も多いようです。
両方とも家庭でエスプレッソを楽しめるマシンですが、構造や操作スタイルにははっきりした特徴があります。
この記事では、2つの違いをやさしく整理しながら、どんな人にどちらが向いているのかを分かりやすくまとめています。

専門的すぎる説明は避け、毎日の生活の中でどう違いを感じやすいのかにフォーカスして解説します。
比較のヒントとして、ぜひ参考になさってください。
▼デロンギ マグニフィカS▼
▼デロンギ クラシック▼
マグニフィカSとクラシックで迷う理由とは?
マグニフィカSとクラシックは、どちらも見かける機会が多く「有名なコーヒーマシン」という印象を持つ方が多いと思います。

そのため、初めて家庭用エスプレッソマシンを検討する人ほど「違いが分からないまま候補に入ってしまう」という状況になりやすいようです。
ここでは、まずこの2台がなぜ比較されやすいのか、その理由を分かりやすく整理していきます。
読み始めの段階で全体像がつかめると、後半の比較ポイントもスムーズに理解できるはずです。
どちらも人気モデルだからこそ悩みやすい
マグニフィカSとクラシックは、どちらも家庭用コーヒーマシンの中ではよく名前が挙がるモデルです。
全自動タイプと手動タイプという違いがあるものの、どちらも「自宅でエスプレッソを楽しめる」という点では共通しています。
そのため、機能の違いをしっかり把握しないまま候補に入ってしまうケースも多く、結果として迷いやすい組み合わせといえます。
また、両モデルともに落ち着いたデザインで、キッチンに置いたときの雰囲気がイメージしやすいことも比較されやすい理由のひとつです。
比較する前に押さえておきたい基本ポイント
本格的な比較に入る前に、まず意識しておくと分かりやすいポイントがあります。
それは「全自動タイプ」と「手動タイプ」では、そもそも操作の考え方が異なるという点です。

例えば、豆を挽く工程や抽出量の調整など、どこまでを自動で行うのか、どこからが自分の操作になるのかによって、使い心地が大きく変わります。
この基本イメージを押さえたうえで読み進めることで、後の章で紹介する違いがより理解しやすくなります。
記事で分かることと読み進めるメリット
この記事では、マシン構造の違いや普段の生活で感じやすい使用感、一般的に語られている意見の傾向まで、幅広く整理していきます。
専門的な表現を極力避けながら、毎日の暮らしの中で「どう違いが出やすいのか」という視点を中心にまとめています。
読み進めることで、ご自身の生活リズムに合いそうなポイントが見えてきやすくなり、どちらを選ぶか考えるヒントにもつながるはずです。
コーヒーマシン選びに悩んでいるときの参考として、ぜひ読み進めてみてください。
コーヒーマシン選びで知っておきたい基礎知識
マグニフィカSとクラシックの違いを理解するうえで、まずは「家庭用コーヒーマシンにはどんなタイプがあるのか」を知っておくと比較がぐっと分かりやすくなります。
ここでは、全自動と手動の一般的な特徴や、豆を挽く機能があるかどうかで変わる使い心地など、基本的なポイントを整理していきます。
これらを押さえておくと、後ほど出てくる細かな違いもイメージしやすくなるはずです。
全自動タイプと手動タイプの一般的な特徴
コーヒーマシンは、大きく「全自動」と「手動」に分かれます。
全自動タイプは、豆挽き~抽出までをマシンがまとめて行ってくれるため、忙しい朝でも短い時間で準備しやすい点が特徴です。
一方、手動タイプは、豆の量やタンピング、抽出のタイミングなど、自分で調整する工程が多く、コーヒーづくりを“作業として楽しめる”という点が魅力とされています。

どちらが良い・悪いというより、生活スタイルによって感じるメリットが異なるタイプといえます。
豆を挽く機能の有無で変わる日常の使い方
「豆を挽く機能」が付いているかどうかは、日頃の使い方や手間に直結する部分です。
豆挽き機能があれば、コーヒー豆を用意するだけで抽出まで進められるため、別でミルを用意する必要がありません。
一方、豆挽き機能がない場合は、事前に豆を挽くか、挽いた豆を購入して使うことになります。
どちらが自分の生活に合うかを考えるうえで、この違いは意外と大切なポイントです。
使用シーンで変わる“相性の良さ”
毎日の使い方をイメージすると、どんなタイプが向いているかが見えやすくなります。
例えば、朝の身支度や家事の合間に「ボタンを押すだけで淹れられると助かる」という場合は、全自動タイプのほうが扱いやすいと感じられるかもしれません。
反対に、休憩時間や休日に「豆を量って、粉をセットして、しっかり抽出するプロセス自体を楽しみたい」という場合は、手動タイプのほうが満足度が高まりやすい傾向があります。
どちらのタイプが“より心地よく感じられそうか”を想像することで、後の比較が一段と理解しやすくなります。
マグニフィカSとクラシックの違いを分かりやすく比較
ここからは、マグニフィカSとクラシックの違いを具体的に見ていきます。
どちらも家庭でエスプレッソを楽しめるマシンですが、構造や操作の仕方、搭載されている機能などは大きく異なります。
この章では、それぞれの特徴を項目ごとにひとつずつ整理しながら、違いをイメージしやすいようにまとめていきます。
ご自身の生活に置き換えて考えながら読み進めてみてください。
マシン構造と操作スタイルのちがい
マグニフィカSは、豆挽き~抽出までまとめて行える全自動タイプという点が特徴です。
操作はボタン中心のため、複雑な工程が少なく、毎日使うときの手間が抑えやすいと言われています。
一方、クラシックは手動で抽出するタイプで、粉量の調整やタンピングなど、自分で扱う工程が多い構造です。
抽出前のプロセスに関わる分、コーヒーづくり自体を楽しみたい方に向けた設計となっています。

どちらも利点が異なるため、日頃どのように使いたいかを基準に考えると選びやすくなります。
豆挽き機能が搭載されているかどうか
マグニフィカSには、豆をそのまま挽けるミルが内蔵されています。
そのため、豆をセットするだけで抽出に進める点が便利とされています。
クラシックは豆挽き機能がない構造のため、あらかじめ挽いた豆を使うか、自分でミルを用意する必要があります。
「豆から挽きたいか、それとも挽いた豆を使うか」によって、日々の使い方にははっきりした差が生まれやすいポイントです。
選べる抽出メニューの幅
マグニフィカSは、全自動マシンらしく複数の抽出設定が用意されています。
ボタン操作で好みの濃さに調整したり、メニューを選んだりしやすい点が特徴です。
クラシックは、手動抽出が基本のため、自分の技量や調整次第で味の変化を楽しみやすいという魅力があります。
決められたメニューを選ぶ便利さを取るか、抽出工程の自由度を楽しむかという違いが表れやすい部分です。
ミルクフォーマー機能の種類と扱いやすさ
どちらのモデルにもミルクを泡立てる機能はありますが、構造や扱いやすさは異なります。
マグニフィカSは全自動タイプらしいシンプルな操作で扱える構造です。
クラシックは、スチーム量の調整など手動要素が強く、フォームミルクづくりを工程として楽しめるタイプといえます。

ラテやカプチーノを作る頻度が高い方は、この違いを意識して選ぶと使い勝手がイメージしやすくなります。
本体サイズ・重さの比較ポイント
本体サイズや重量は、キッチンやカウンターに置いたときの取り回しに関わる部分です。
一般的に、全自動マシンは内部構造が複雑なためサイズが大きくなりやすく、手動マシンは比較的コンパクトな傾向があります。
とはいえ置き場所との相性は家庭ごとに異なるため、事前に設置スペースを測っておくのがおすすめです。
このあと登場する「設置スペースの注意点」の章と合わせてチェックしてみてください。
▼デロンギ マグニフィカS▼
▼デロンギ クラシック▼
メンテナンス性の違いと取り扱いのしやすさ
コーヒーマシンを選ぶうえで意外と大切なのが、お手入れのしやすさです。
毎日使う家電だからこそ、後回しにしなくて済むメンテナンス性は満足度に直結しやすいポイントです。
ここでは、マグニフィカSとクラシックのメンテナンスまわりの傾向を、一般的に語られている特徴として整理していきます。
毎日のお手入れの手間に関する一般的な違い
マグニフィカSは、全自動構造という性質上、内部の自動洗浄機能が搭載されています。
電源のオン・オフ時に内部を洗い流す動作を行うモデルが多いため、日々の手洗い部分が少なめと感じられやすい傾向があります。
一方でクラシックは、手動抽出タイプのため、ポルタフィルターの洗浄やスチームノズルのケアなど、手を動かす工程が多くなりやすいのが特徴です。

この違いは、マシン自体の構造によるものなので、「どれくらいの頻度で使うか」「どのくらい手入れの時間が取れるか」を基準に考えると選びやすくなります。
タンクやトレイなど取り外しやすさの比較
どちらのマシンにも給水タンクやドリップトレイがありますが、取り外し方や構造には差があります。
マグニフィカSは比較的シンプルに着脱しやすい構造が採用されているため、日常的なお手入れの負担を抑えやすいとされています。
クラシックは、必要なパーツを自分の手でしっかり扱う工程が多いため、慣れるまでは少し丁寧さが求められる場面があるようです。
ただ、どちらも家庭用として扱える設計で作られているため、「自分の性格や生活リズムと合うか」で考えるのがポイントです。
長く使うために意識したいケアのポイント
コーヒーマシンを長く使うためには、日頃の簡単なケアが役立ちます。
一般的には、給水タンクの洗浄や抽出口の拭き取りなど、短時間で終わるメンテナンスをこまめに行うことで、機械のコンディションを保ちやすくなるとされています。
クラシックのように手動操作が多いタイプは、抽出後の後片付けも一連の流れとして扱うことが多いため、こうした工程を“楽しめるかどうか”も相性の判断材料になります。
メンテナンス性は、快適に使い続けられるかを左右する部分でもあるため、比較するときのひとつの軸として意識してみてください。
| 項目 | マグニフィカS | クラシック |
|---|---|---|
| 日々のお手入れ | 自動洗浄などで手順が少なめ | 手動ケアが中心 |
| パーツの着脱 | シンプルで扱いやすい構造 | 慣れるまで丁寧さが必要 |
| ケアの性質 | 時短しやすい | 工程を楽しめる傾向 |
使用シーン別:どんな人にどちらが向いている?
ここでは、マグニフィカSとクラシックがどんな使い方に向いているかを「生活シーン」ごとに整理していきます。
スペックの比較だけではイメージしにくい部分も、日常の動きに照らし合わせることでグッと分かりやすくなります。
毎日のコーヒータイムをどんなふうに過ごしたいのかを考えながら読み進めてみてください。
朝の支度の合間にサッと淹れたい場合
忙しい朝や、仕事や家事の合間に「早く飲みたい」というシーンでは、全自動タイプの特徴が活かされます。
マグニフィカSのように豆挽き~抽出までを自動で進められるタイプは、手順が少なく準備の負担が抑えやすい点が魅力です。

抽出中に別の家事を進められるケースも多く、短時間で整えやすい使い方との相性が良いとされています。
忙しい時間帯でもコーヒーを楽しみたい方は、この点が判断材料になりやすい部分です。
一杯ずつ味わいながら淹れたい場合
ゆっくり時間がとれるときに、「抽出工程そのものを楽しみたい」という場合は、手動タイプのクラシックのようなマシンが向いているケースがあります。
粉の量を調整したり、タンピングの力加減を変えてみたり、湯量やタイミングを少しずつ調整することで、自分好みの一杯を探していく工程を楽しめる点が特徴です。
抽出の過程をじっくり味わう時間そのものを大切にしたい場合、手動マシンならではの魅力を感じやすくなります。
置き場所や生活導線から見た相性
実際に使ううえでは、置き場所や家の導線も意外と重要なポイントです。
キッチンカウンターのスペースが限られている場合は、比較的コンパクトな手動モデルのほうが置きやすいケースがあります。
一方で「毎回の設置や片付けが負担に感じそう」という場合は、多少サイズが大きくても全自動タイプのほうが結果的に扱いやすい場面もあります。

日々の生活導線をイメージしながら、「どの位置に置いて、どんな動きで使うか」を考えることで、相性が見えやすくなるはずです。
| シーン | マグニフィカS | クラシック |
|---|---|---|
| 忙しい時間帯 | 短時間で準備しやすい | 工程が多いため落ち着いた時間向き |
| コーヒーを淹れる工程を楽しみたい | 操作はシンプル | 調整しながら淹れる過程を楽しめる |
| 設置スペース | サイズが大きくなりやすい傾向 | 比較的コンパクトに置きやすい |
▼デロンギ マグニフィカS▼
▼デロンギ クラシック▼
一般的に報告されている使用感の傾向
ここでは、マグニフィカSとクラシックについて、ネット上で見られる声の傾向をもとに「どんな印象が語られていることが多いのか」をまとめています。
特定サイトのレビューを引用するのではなく、あくまで広く見られる意見の方向性として整理しています。
機種ごとの単なる評価ではなく、「どういう点が話題にされやすいか」を知ることで、ご自身が重視したいポイントを見つけやすくなります。
マグニフィカSに関する声の主な傾向
マグニフィカSは、全自動タイプの特性から「扱いやすさ」について触れられていることが多い傾向があります。
豆挽き~抽出までひとつの流れで進められるため、毎日のルーティンに組み込みやすいという意見が目に入りやすいようです。
また、ボタン操作で設定できる部分が多いことから「初めてでも扱いやすそう」という印象を持たれやすい点も特徴とされています。
一方で、全自動機ならではの構造により「サイズ感」を気にする声が見られることもあります。
クラシックに関する声の主な傾向
クラシックは手動抽出タイプのため、「自分で調整しながら淹れられる楽しさ」に触れた意見が見られることが多いようです。
タンピングや抽出量の調整など、工程が多い分、自分の好みを探していくプロセスに魅力を感じる人が一定数いる印象です。
また、比較的コンパクトに置ける点について言及されることもあり、小さめのキッチンでも扱いやすいという視点で話題にされるケースも見られます。
その一方で、手動タイプゆえに「扱いに慣れるまで少し時間が必要」という声が出る場面もあります。
使用者の多くが気になりやすいポイント
どちらのマシンにも共通して話題に上がりやすいのが、「毎日の手入れのしやすさ」と「稼働音」に関する部分です。
コーヒーマシンは構造上、抽出時の音がある程度発生するため、静音性を重視する方は事前にイメージしておくと良い場合があります。
また、お手入れのしやすさは利用頻度に直結しやすく、特に忙しい生活の中では負担に感じるかどうかが気になりやすいポイントです。
これらの傾向を知っておくことで、自分がどこを重視したいかが自然と浮かび上がってくるはずです。
| 項目 | マグニフィカS(傾向) | クラシック(傾向) |
|---|---|---|
| 扱いやすさ | 全自動のため手順が少ない印象 | 慣れるまで工程が多め |
| 抽出の楽しさ | ボタン操作で簡単 | 手動で調整する楽しさが話題に |
| 置きやすさ | サイズ感を気にする声あり | 比較的コンパクトとされる傾向 |
| 音やお手入れ | 自動洗浄などで手間が少ない印象 | 手動ケアが話題にされることが多い |
▼デロンギ マグニフィカS▼
▼デロンギ クラシック▼
ラテやカプチーノを楽しむためのポイント
ミルクを使ったドリンクを楽しみたい方にとって、フォームミルクのつくりやすさは気になるポイントのひとつだと思います。
ここでは、ラテやカプチーノを作るときに押さえておきたい一般的なコツや、ミルクの種類による違いなどをまとめました。
特定のモデルの優劣を示すものではなく、家庭でミルクメニューを楽しむ際のヒントとして読み進めてみてください。
ミルクの種類で変わる泡立ちの傾向
フォームミルクをつくるときは、使うミルクの種類によって泡立ち方に違いが出やすいとされています。
一般的には、脂肪分のバランスによって泡のきめ細かさやコクが変化しやすく、成分調整乳よりも成分無調整のほうが泡立ちやすいと感じられるケースがあります。

また、低脂肪乳は軽い泡になりやすいなど、種類ごとの傾向を知っておくと目的の仕上がりに近づけやすくなります。
これはどのマシンでも共通して語られるポイントで、豆や抽出と同様、ミルク選びも仕上がりに影響しやすい部分です。
ラテアートを楽しみたい場合に知っておきたいこと
ラテアートは、フォームミルクのきめ細かさや温度が大きく関わるため、慣れるまでは難しく感じやすい場合があります。
一般的には、ミルクの温度が高すぎると泡が粗くなり、低すぎると柔らかくならないといわれています。
一定の温度帯で加熱しながら均一に空気を含ませることで、滑らかなフォームに仕上がりやすくなります。

家庭用マシンでも工夫次第で楽しめる取り組みなので、抽出時間そのものを楽しみたい方にはチャレンジしやすい要素です。
自宅でミルクフォームを活用する際のコツ
家庭でラテやカプチーノを淹れるときは、以下のような一般的なコツが役立つことがあります。
*冷たいミルクを使うと温度管理がしやすい
*スチームノズルはミルク表面ぎりぎりに位置させる
*大きすぎないピッチャーを使うと泡がつくりやすい
*注ぐタイミングを安定させると、きれいに仕上がりやすい
これらは特定のマシンに依存しない基本的なポイントで、どの機種でも応用しやすい部分です。
毎日のコーヒータイムにミルクドリンクを取り入れたい方は、こうしたコツを意識してみると好みの仕上がりに近づけるきっかけになるはずです。
| ミルクの種類 | 泡立ちやすさの傾向 | 仕上がりの特徴 |
|---|---|---|
| 成分無調整乳 | 泡立ちやすい傾向 | なめらかでコクが出やすい |
| 成分調整乳 | やや泡が軽め | 口当たりが軽い仕上がりになりやすい |
| 低脂肪乳 | 軽い泡になりやすい | スッキリめの風味 |
設置スペースと電源まわりで気を付けたいこと
コーヒーマシンを選ぶときは、機能や味の違いだけでなく「置き場所との相性」もとても大切です。

毎日使う家電だからこそ、置きやすさや動線の取りやすさは使い勝手に直結しやすいポイントです。
ここでは、マシンの種類に関係なく家庭用コーヒーマシン全般に当てはまる注意点を、一般的な観点からまとめています。
キッチンで置き場所を選ぶときのチェックポイント
コーヒーマシンを設置する位置を決める際は、以下のような基本的な点が役立ちます。
*給水タンクを取り外せるスペースが確保できるか
*ドリップトレイや内部パーツの手入れがしやすい位置か
*抽出口の下にカップを置く作業がスムーズか
*蒸気や熱がこもりにくいかどうか
特に全自動モデルの場合、開閉する部分が複数あるため、前後左右のスペースを少し余裕を持って確保しておくと扱いやすくなります。

手動タイプの場合は、抽出時にポルタフィルターを扱う動線が必要になるため、操作しやすさをイメージしておくと安心です。
電源容量の一般的な目安
家庭用コーヒーマシンは、加熱や圧力を使う工程が多いため、一定の電力を必要とします。
一般的には、電子レンジや電気ケトルと同じように、同一コンセントで高出力家電を同時に使うとブレーカーに負担がかかるケースがあります。
そのため、延長コードの使用やタコ足配線を避け、単独で使えるコンセントに設置するほうが安心とされています。
電源周りは安全に関わる要素でもあるため、事前に配置を考えておくとより快適に使いやすくなります。
お手入れスペースも含めた実寸の考え方
マシンのサイズは、幅や奥行きだけでなく「実際に使うときに必要になるスペース」も含めて考えるのがおすすめです。
例えば、上部に給水タンクがあるモデルは、上方向にスペースが必要になることがあります。

また、抽出後の掃除やパーツの取り外しなど、日常的なケアの動きを考えることで、ストレスなく使い続けられる設置環境をつくりやすくなります。
マシン自体の寸法と、周囲に必要な余白をあわせて把握しておくと、置いた後の使い勝手が変わりにくくなります。
| 項目 | チェック内容 |
|---|---|
| スペース | 給水タンク・ドリップトレイがスムーズに取り外せるか |
| 動線 | カップの置き替えや操作がしやすいか |
| 電源 | 単独のコンセントが使える位置にあるか |
| 周囲環境 | 蒸気や熱がこもりにくいかどうか |
マグニフィカSとクラシックの主要スペック一覧
ここでは、マグニフィカSとクラシックの仕様を整理し、特徴を一度に確認できるよう一覧形式でまとめていきます。
スペックを並べて見ることで、どちらにどんな機能が備わっているのか、客観的に把握しやすくなります。
あくまで一般的に公開されている仕様をもとにした比較で、特定モデルを優劣で判断する内容ではありません。
基本仕様の一覧
下記は、全自動タイプと手動タイプの違いが分かりやすいよう、主要項目をピックアップした表です。
| 項目 | マグニフィカS(ECAM22112B) | クラシック(EM450J-M) |
|---|---|---|
| タイプ | 全自動エスプレッソマシン | 手動エスプレッソマシン |
| 豆挽き機能 | あり(内蔵ミル) | なし(別途ミルが必要) |
| 抽出方式 | 自動抽出 | 手動抽出 |
| ミルクフォーマー | あり | あり |
| 操作スタイル | ボタン中心 | レバー・ボタン・タンピング操作 |
抽出方式の違い
抽出方式には、全自動と手動という大きな違いがあります。
マグニフィカSは抽出までの工程をまとめて行えるため、機械に任せる割合が高い方式です。
一方でクラシックは、自分で粉をセットし、圧力のタイミングを見ながら抽出するため、工程全体をコントロールしやすいスタイルです。

この違いは、日々の操作手順や味の調整しやすさにも影響しやすいポイントとなります。
給水タンクや対応豆に関する一般的仕様
給水タンクや使用できる豆に関しては、以下のような一般的な特徴があります。
*マグニフィカS
→ 豆から挽けるため、焙煎豆をそのまま使える
*クラシック
→ 事前に挽いた豆、または自分でミルを使って挽いた豆を使用
また、給水タンクの容量はモデルによって異なりますが、どちらも家庭用として扱えるサイズ感が採用されています。
スペックを比較するときは「機能の有無」だけでなく、「自分の使い方にどれが必要なのか」を基準に見ていくのがおすすめです。
▼デロンギ マグニフィカS▼
▼デロンギ クラシック▼
よくある質問(FAQ)
ここでは、マグニフィカSやクラシックの購入を検討している方から寄せられやすい疑問を、一般的な範囲でまとめています。
細かな仕様はモデルによって異なることがありますが、家庭用コーヒーマシン全体に共通しやすいポイントを中心に整理しています。
購入前の不安を解消しやすくなる項目ばかりなので、気になるところをチェックしてみてください。
ドリップコーヒーとエスプレッソの違いは?
ドリップはお湯をゆっくり注いで抽出する方法で、すっきりした風味になりやすいのが特徴です。
一方、エスプレッソは圧力をかけて短時間で抽出するため、濃厚で香りが凝縮された一杯になりやすい傾向があります。

この2つは抽出方式が大きく異なるため、風味や口当たりにも違いが出やすく、好みによって選ぶポイントが変わります。
どんな豆が使える?
マグニフィカSは豆を挽ける全自動タイプのため、一般的な焙煎豆をそのまま使用できます。
クラシックは豆挽き機能がない構造のため、挽き豆を使うか、自分でミルを用意して粉にしたものを使用する形になります。
どちらの場合も、焙煎の度合いや豆の種類によって味わいは変わるため、自分の好みに合わせて選んでいくと楽しみが広がります。
一般的なランニングコストの目安は?
ランニングコストは、主に「コーヒー豆(または挽き豆)」「水」「電気代」「消耗品の買い替え」などが含まれます。
特に豆の価格は種類によって幅があるため、日頃どのくらいの頻度で淹れるかがコストの変動要因になりやすい部分です。
また、ミルクドリンクをよく作る方は、ミルクの購入量も自然と増える場合があります。

どのマシンでも、一般的な家庭用コーヒーマシンとして大きく異なる部分ではないため、日々の消費量に合わせて考えるのがおすすめです。
手入れはどれくらいの頻度で必要?
家庭用コーヒーマシンは、毎回の軽い掃除と、定期的な深めのメンテナンスを組み合わせて使われることが一般的です。
*給水タンクの洗浄
*抽出口周りの拭き取り
*ミルクフォーマーやスチームノズルのケア
*ドリップトレイの洗浄
こうした日常のメンテナンスに加えて、内部洗浄が必要な場合もあります。
マグニフィカSのように自動洗浄機能があるモデルは負担が少ないと言われる傾向がありますが、クラシックのような手動モデルは丁寧なケアが必要な場面が見られます。
どちらの場合も、定期的な手入れが長く使うためのポイントです。
購入前に確認しておきたいチェックリスト
ここでは、マグニフィカSとクラシックのどちらを選ぶ場合でも役立つ「購入前チェックポイント」をまとめています。
スペック表だけを見て選ぶと、実際に使い始めてから「思っていた動きと違う…」と感じやすい場合があります。
生活動線や手入れの負担など、日常で“使う時間帯”や“使う場所”をイメージしながら確認してみてください。
置き場所のサイズと動線
コーヒーマシンはキッチン家電の中でも存在感があり、置き場所の相性がとても大切です。
確認したいポイントとしては以下のような点があります。
*設置予定のスペースに収まるか
*前後左右にある程度の余白が取れるか
*給水タンクを取り外す動線が確保できるか
*カップの置き替えがスムーズにできるか
特に全自動タイプは内部構造が複雑なため、想像以上に“前後のスペース”が必要になる場合があります。
手入れにかけられる時間
お手入れが負担に感じるかどうかは、マシンとの相性に大きく関わります。
次のような点を事前にイメージしておくと安心です。
*毎回の軽い掃除をどれくらい負担に感じるか
*水タンクやパーツの洗浄を続けられそうか
*ミルク系のドリンクを作る頻度は多いか
マグニフィカSのような全自動タイプは手順が少なめですが、クラシックのような手動タイプは工程が多いため、手入れ時間もライフスタイルに合わせて考えるのがおすすめです。
毎日の利用場面を思い浮かべてみる
コーヒーを淹れるタイミングは、人によって大きく違います。
*朝の短時間で飲むのか
*夜のリラックス時間にゆっくり淹れたいのか
*家族全員で使うのか、一人で使うのか
こうした“使うシーン”を考えてみると、全自動のほうが向いているのか、手動が楽しめそうなのかが自然と見えてきます。

使い始めてからギャップが生まれやすい部分なので、事前に整理しておくと安心です。
全自動・手動どちらが自分に合うかの確認項目
最後に、迷っている方のヒントとして、一般的に役立つチェック項目をまとめました。
| 項目 | あてはまる内容 |
|---|---|
| 手軽さ | ボタン操作で淹れられるほうが助かる → 全自動が向きやすい |
| 工程の楽しさ | 豆量や抽出を自分で調整したい → 手動が楽しみやすい |
| 置き場所 | スペースに余裕がある → 全自動 コンパクトに置きたい → 手動 |
| メンテナンス | お手入れを簡単に済ませたい → 全自動 ケアも含めて楽しみたい → 手動 |
この章のチェック項目を参考にしながら、ご自身の暮らしに合う選び方を考えてみてください。
マグニフィカSとクラシックの比較まとめ
ここまで、構造や操作スタイル、メンテナンス性、使用シーン、そしてネット上で見られる意見の傾向などをもとにマグニフィカSとクラシックの特徴を整理してきました。
最終章では、内容の振り返りと一緒に「どんな基準で選ぶと自分に合った1台が見つけやすいか」をまとめていきます。
迷っている場合は、ここで一度ポイントを再確認してみてください。
この記事の要点まとめ
マグニフィカSとクラシックの違いは、大きく次のような傾向に集約されます。
操作のちがい
マグニフィカSは全自動で手順が少なめ。
クラシックは手動で抽出工程を自分で扱うタイプ。
豆挽きの有無
マグニフィカSは豆挽き機能つき。
クラシックは別でミルが必要。
メンテナンス
全自動は日々の負担が抑えやすい傾向。
手動は日常的なケアが使用工程に含まれやすい。
置き場所との相性
全自動はサイズが大きくなりやすい。
手動はコンパクトに置きたい人と相性が良い。
使用感の傾向
マグニフィカSは扱いやすさが語られやすい。
クラシックは工程を楽しめる点が話題になりやすい。
2つの違いを踏まえた選び方の整理
マシン選びで大切なのは、「どちらが優れているか」ではなく「どちらが自分の生活に合っているか」という視点です。
次のように考えると、選ぶ基準が見つけやすくなります。
時間をかけずに淹れたい
→ 全自動のマグニフィカSの使い方がイメージしやすい。
抽出工程もコーヒー時間の一部として楽しみたい
→ 手動のクラシックが馴染みやすいケースがある。
置き場所に余裕がない
→ 比較的コンパクトなクラシックが候補に入りやすい。
お手入れをできるだけシンプルにしたい
→ 自動洗浄機能のある全自動タイプが向く場面もある。
▼デロンギ マグニフィカS▼
▼デロンギ クラシック▼
最後に:迷っている人へのヒント
コーヒーマシンは毎日の生活に寄り添うアイテムなので、「どんな時間を過ごしたいか」をイメージすることがとても大切です。

朝の忙しい時間帯や、ゆっくりしたい夜のひとときなど、使う場面を思い浮かべながら考えると、自然と自分にしっくりくるマシンが見えてくるはずです。
ここまでの比較が、マグニフィカSとクラシックを選ぶときのヒントになれば嬉しいです。
ご自身の生活スタイルに合う1台を、ぜひ見つけてみてください。